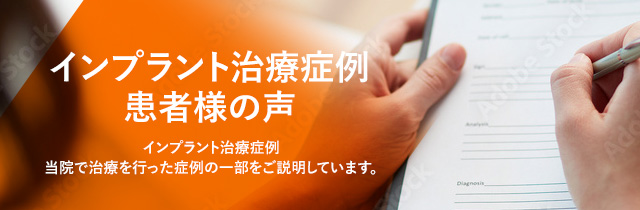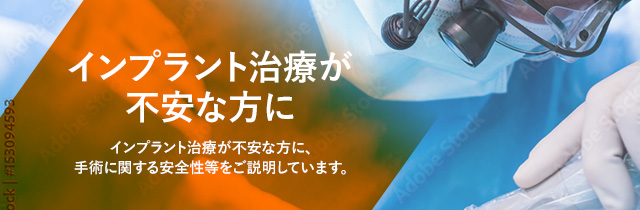歯がグラグラするのは危険信号!放置するとどうなる?

「歯がグラグラする」感覚を覚えたことはありませんか。噛むたびに揺れる、歯ぐきが下がってきた気がする――そうしたサインは、歯周病や噛み合わせの不調など、見過ごせないトラブルの前触れである可能性があります。放置すれば、最終的に歯を失う事態に至ることもあります。
本記事では、揺れの原因、放置によるリスク、歯科医院で実施する主な対処までを、東陽町駅から徒歩0分の歯医者・ナオデンタルクリニックが専門的視点でわかりやすくご説明します。
目次
歯がグラグラするのはなぜ?主な4つの原因
歯が揺れる、グラグラする主な原因としては以下の4つが挙げられます。
歯周病で支えを失う
歯が動揺する最大の要因は歯周病です。歯を支える歯槽骨や歯ぐきが慢性の炎症で徐々に損なわれ、支台が弱ることで歯が動きやすくなります。初期は痛みが乏しく進行に気づきにくいため、出血、口臭、歯が浮くような違和感がある段階で早めに受診することが重要です。
咬合(噛み合わせ)の不均衡
歯並びの乱れや欠損の放置によって噛み合わせが崩れると、一部の歯に力が集中し、歯根膜(歯の根を支えるクッションの役割をもつ組織)や骨へ過剰な負担がかかります。合わない詰め物・被せ物による微妙な高さの差も不調和を助長し、動揺や歯ぐきの退縮を引き起こす原因になります。
外傷・食いしばり・歯ぎしり
転倒や打撲などの外傷に加え、無意識の食いしばり・歯ぎしりは毎日のように長時間の力を加えます。微細な損傷が積み重なることで歯が緩んだり、歯根に亀裂が入ったりすることもあります。就寝時に症状が疑われる場合、マウスピースでの保護が有効です。
矯正治療に伴う一過性の動揺
歯列矯正では骨の改造を伴う歯の移動によって、治療中に軽いグラつきが生じることがあります。多くは数週間~数か月で安定しますが、揺れが強い、噛むと痛むなどの症状が続く場合は、早期の診察が必要です。
歯がグラグラしたとき絶対やってはいけないこと

指や舌で動かして確かめる
歯が揺れる感覚があると、つい舌や指で触って確かめたくなります。しかし、これは非常に危険な行為です。歯の根を支える「歯根膜」は、噛む力を分散し歯を安定させる重要な組織で、繊細な神経と血管が通っています。繰り返し押すことで歯根膜が炎症を起こし、修復が遅れるだけでなく、歯槽骨の吸収を助長してしまうこともあります。自覚的なグラつきがある場合は、触れずに安静にして、早めに歯科医院で診査を受けましょう。
硬い食べ物を無理に噛む
ナッツやスルメ、堅いパンなどを無理に噛むと、動揺している歯に強い咬合圧が加わり、歯根膜炎や歯根破折を起こすおそれがあります。歯がグラついているときは、咀嚼時の力が均等に伝わらず、一部の歯に過度な負担が集中します。症状がある間は柔らかい食事を心がけ、左右どちらか一方で噛む「片噛み」も避けるようにしましょう。咀嚼のバランスを保つことが、歯周組織へのダメージを最小限にするポイントです。
自己判断で放置する
「そのうち治るだろう」と放置するのは最も危険です。歯がグラグラしている状態は、歯を支える歯周組織(歯ぐき・歯根膜・歯槽骨)のいずれかが損傷していることを意味します。特に歯周病が原因の場合、時間の経過とともに骨吸収が進み、最終的に歯が自然に脱落することもあります。早期に歯周検査やレントゲン撮影などの診査を受ければ、炎症の段階で治療を行い、骨吸収の進行を抑えることが可能です。適切な介入こそが、歯を守る最短の道です。
放置するとどうなる?歯のグラつきが招く深刻なリスク

歯がグラグラする症状を軽視して放置すると、次に挙げるようなリスクが生じます。
歯槽骨のさらなる吸収
歯周病の進行により、歯を支える歯槽骨が持続的な炎症で破壊されていくと、歯の動揺は急速に悪化します。歯周病原菌の毒素や炎症性サイトカイン(IL-1β・TNF-αなど)が骨吸収を促進し、骨の再生と破壊のバランスが崩れることで、支持組織が減少していきます。 骨が失われると歯の支えが弱まり、最終的には自然脱落に至るケースも少なくありません。早期に炎症をコントロールし、必要に応じて再生療法(GTR法やエムドゲイン法など)を行うことで、失われた骨組織の再建が期待できます。
噛み合わせ全体の崩壊
1本の歯が動揺すると、噛み合わせ(咬合バランス)全体に影響を及ぼします。特定の歯に過剰な力が集中することで、咬合性外傷が発生し、他の歯や顎関節にまで負担が広がります。この状態が続くと、複数の歯が次々と動揺し、咬合全体の安定性が失われる「ドミノ現象」が起こります。結果として咀嚼機能が低下し、顎関節症や頭痛・肩こりといった二次的症状が現れることもあります。歯を支える力学的バランスを保つには、早期の咬合調整が重要です。
歯ぐきの炎症・口臭・審美性の低下
歯がグラグラする状態では、歯と歯ぐきの間に歯周ポケットが形成され、嫌気性細菌(ポルフィロモナス・ジンジバリスなど)が繁殖しやすくなります。これにより歯ぐきの腫れ、出血、膿の排出、さらには強い口臭が生じます。 また、慢性的な炎症によって歯ぐきが退縮すると、歯が長く見える「歯肉退縮」が起こり、見た目の印象にも大きく影響します。歯周組織の炎症を抑えるには、専門的な歯周治療とプラークコントロールの両立が欠かせません。
全身状態への波及
重度の歯周病は、もはや口の中だけの問題ではありません。近年の研究では、歯周病による慢性炎症が糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞、早産、アルツハイマー病などの発症・悪化に関与することが報告されています。リスクを下げる意味でも、口腔内の炎症コントロールは重要です。 歯周病原菌や炎症性物質が血流を介して全身に広がることで、動脈硬化やインスリン抵抗性の増強を引き起こすと考えられています。したがって、歯がグラグラする症状を軽視せず、口腔の炎症を早期に治療することは、全身の健康維持にもつながります。
歯医者で行う主な治療法

歯がグラグラする症状は、歯医者で行う治療法で改善できる場合があります。
歯周基本治療・外科治療・再生療法
原因が歯周病であれば、まずスケーリング・ルートプレーニングで歯石・細菌を徹底除去し、歯ぐきの炎症を鎮めます。進行例では、感染組織を取り除く歯周外科を行うことがあり、骨欠損が大きい症例では人工骨や再生誘導材を用いた歯周組織再生療法で骨支持の回復を目指します。早期介入がその後の回復を大きく左右します。
動揺歯の一時固定(スプリント)
揺れが強い場合は隣在歯と連結して一時的に固定し、負担を分散させて歯根膜・骨の回復を促します。固定はあくまで補助的措置であり、並行して原因治療を進めることが不可欠です。
咬合調整と欠損補綴
力の集中を避けるために歯の高さを微調整し、噛み合わせの均衡を整えます。欠損がある場合はブリッジやインプラント等で機能を補い、特定の歯への負荷を軽減します。
生活習慣の是正と定期メンテナンス
就寝時のナイトガードで食いしばり・歯ぎしりの力から歯を守り、歯間ブラシやフロスを用いたセルフケアを身につけます。治療後も3〜6か月ごとの定期検診で歯ぐきや骨の状態を確認し、再発を予防します。
まとめ
歯がグラグラする状態は、口腔が発する明確な警告です。歯周病や噛み合わせの乱れが背景にあることが多く、自然に治るケースはほとんどありません。進行すれば抜歯に至る可能性もあるため、早期の評価と治療が肝心です。ナオデンタルクリニックでは、原因を丁寧に見極め、可能な限り歯を守ることを目標に治療計画をご提案します。「最近、歯が揺れる気がする」と感じたら、どうぞお早めにご相談ください。
最新記事 by 高峰 直努 院長 (全て見る)
- テストナオデンのインプラントブログ個別記事のタイトル テストナオデンのインプラントブログ個別記事のタイトル - 2021年10月25日